みなさんこんにちは、このブログを書いている東急三崎口です。
この記事は、長期連載の第5回として、電子とホールの意味合いと実用上のふるまいについて書いていきます。
本連載で扱っているのは、S.M.Sze著の半導体デバイス第2版の日本語訳verです。興味のある方は、下記リンク先から見てみてください。
前回の記事である、第4回はこちらです。

この記事のポイント
この記事は、原著ではさらっと書かれている部分に対して、補足する内容を書いているので原著のページは特にありません。
本記事で扱う内容
【内容】
・電子とホールの位置づけ
・ホールって本当に必要なの?
【ページ】
・特に無し
電子とホールについて書いていくので、理工系の大学生レベルの基礎知識が必要になってきます。
できるだけ、基礎知識が無くても読めるように情報を追加して書いていますが、原著が前提にしている背景知識は理工系の大学生レベルなのでご了承ください。
【ポイント】
・電子は電子、ホールは電子が抜けた穴
・ホールは電子の穴として説明されるが、実用上は正電荷として扱ってさしつかえない
電子とホール
電子とホールについて、簡単に触れておいた方がいいと思ったので、原著で参照するページは無いのですが、追加で記事を書いています。
電子とホールという呼び方自体も少し変で、本来は「電子と正孔」か「ElenetronとHole」と書くべきなのでしょう。
ただ、電子とホールと呼ばれることもそれなりにあるので、このような書き方をしています。
電子については、金属の中での振る舞いがよく知られています。金属は、自由電子を持っているので、電気や熱をよく伝えると説明されます。
半導体における電気伝導を担っているのは電子とホールです。金属の場合は電子ですが、半導体の場合はN型は電子が、P型はホールが電気伝導を担っているとよく言われます。
N型の場合は、電子をSiより多く持っている原子が不純物として加えられて、余った電子が半導体の中の電気伝導を担うとされています。
P型の場合は、Siより電子が少ない原子が、不純物として加えられて、電子の穴のようなものが発生し、これをホールと言います。そして、ホールが電気伝導を担うと説明されます。
教科書的には、N型では電子が、P型ではホールがキャリアとして働くと思っていればいいわけです。ただ、かつて半導体デバイスを勉強していた時の私は、どうしても一つの疑問が生じたんです。
ホールは電子の穴のようなものであれば、電子だけで統一的に電気伝導を説明すればいいのに、あえてプラス電荷のホールなるものを導入しなければいけない理由はどこにあるのだろうか?という問いです。
ホールって本当に必要なの?
結局のところ、電子とホールを導入することで、実用上半導体デバイスの理解がしやすくなるという面は非常に大きいです。
多数キャリアはN型では電子、P型ではホールだと考えることで、PN接合ダイオードや、受発光デバイスの理解がしやすくなります。
電子とホールの2つのキャリアを仮定しないと説明できない現象は何だろうか?と考えた時に、私が現実として実感したのはホール効果測定でした。
ホール効果測定は、前にちょっとマニアックな記事を書きました。

ホール効果測定は、電流を印加した試料に対して、磁場を電流と垂直に印加することで、キャリアの種類(要はPかNか)と移動度を測定できる実験です。
実験自体は、semi-journalさんのサイトでわかりやすく説明されています。
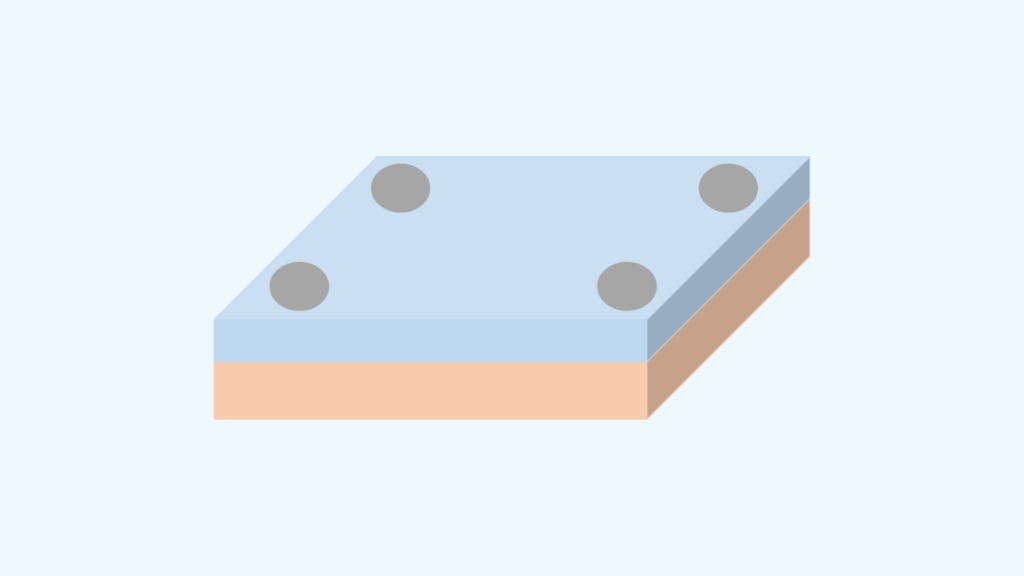
この時に、電流を同じ方向に流しているのに、キャリアの種類によって生じるホール電圧が逆になります。この効果を利用して、キャリアの種別を判定しているわけですが、電流と磁場の相互作用という観点で見ると、電子とホールの差分が見えてきます。
電子はマイナスの電荷を持っていて、電流の向きとは逆の方向にキャリアが動いています。ホールはプラスの電荷を持っていて、電流と同じ向きにキャリアが動いていると考えられています。
電流を流すと、キャリアが移動すること自体は一緒なんですが、磁場が印加された時のふるまいが変わります。
要は、磁場印加に対してホールは電子と逆のふるまいをするわけです。
この実験事実から、半導体のキャリアを考えるときに、磁場に対する応答が変わる2種類のキャリアが存在すると仮定せざるを得ないのではないかと感じました。
ホールが電子の穴ならば、2種類のキャリアを仮定する必要があるのだろうか?という問いに対しては、磁場に対する応答が違うので2つのキャリアを仮定せざるを得ない実験事実があるというのが、現段階での私の答えです。
電子もホールも、肉眼で見ることはできないので、直接ふるまいを観察するのは難しいですが、このような理解をしています。
もっと詳しく電子とホールを仮定しないといけない理由を知っている方がいらっしゃれば、教えてくださると幸いです。
まとめ
この記事では、S.M.Szeを読み解く連載の第5回として電子とホールの意味合いと実用上のふるまいについて書きました。
今回の記事では、S.M.Szeに直接載っているわけではないものの、今後長いお付き合いになる電子とホールについて取り上げてみました。次回からは、S.M.Szeの内容に戻ります。
この連載では、S.M.Szeの内容について取り上げているので、わからない点や聞いてみたいことがあればQ&Aとして取り上げていきたいと思っています。コメント欄か、下記のお問い合わせフォームからご連絡いただければ、お返事いたします。
前回の記事である、第4回はこちらです。

このブログでは、半導体に関する記事を他にも書いています。半導体メモリ業界が中心ですが、興味がある記事があれば読んでみてください。





この記事はここまでです。最後まで読んでくださってありがとうございました。








コメント